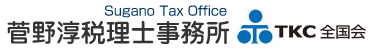宝暦治水
国税庁のメールマガジン(7月)に宝暦治水が紹介されていました。
宝暦治水とは江戸時代の宝暦年間(1754年~55年)に、幕府の命令により
薩摩藩が行った治水工事です。
濃尾平野の治水対策で、木曽川、長良川、揖斐川の三川分流を目的とした
難工事でした。
砂糖貿易で潤っていた薩摩藩の財力を弱める目的で工事が課せられました。
幕府は工事の遂行や工事に当たった藩士の食事内容に到るまで様々な
制約を課しました。
赤痢の流行による病死者、抗議のための自害者をあわせて百人近くの犠牲者
を出しました。
工事には現在の貨幣価値に換算して300億円以上費やしました。
この事件は幕末の討幕運動の原因となりました。
工事をやり遂げた藩士は「薩摩義士」と称されます。
幕府と一戦交える代わりに、民のために工事をやり遂げたのです。
幕府は政権維持のために、外様の大藩である薩摩の財力を弱める必要がありました。
「民を救う」ことよりも「薩摩を弱める」ことが目的でした。
そのために必要だったのが「いやがらせ」でした。
みっともない施策は、大きなしっぺ返し(倒幕)となって返ってきました。